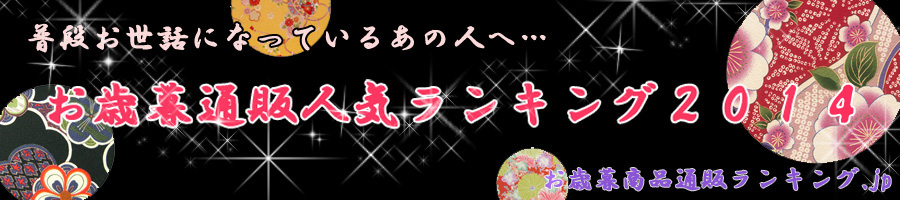お歳暮の起源


そもそもお歳暮とは、どのようにして始まり、どのように伝わっていったのでしょう。
その起源には諸説ありますが、一説にはその昔、お嫁に行った女性が毎年実家で奉っていた神様へのお供え物として実家へ贈り物をするようになったのが始まりだと言われています。
贈り物の内容は鮭や数の子等、様々だったようですが
決まって「食料品」を奉納していたと言います。
これがやがて”実家と嫁ぎ先とを結ぶ潤滑剤”としてとらえられるようになり、
結婚の際の仲人さんにも贈り物をするようになったのです。
次第にその範囲は広がっていき、
最終的には”日頃お世話になっている人たちへの贈り物の習慣”ということで落ち着きました。
お歳暮とお中元の関係
お歳暮はお中元とセットで考えられることが多いですよね。
これは日本の古来の「一年両分制度」に基づいているからなんです。
一年両分制では一年を前半と後半の2つに分け、丁度中間のお盆と年末にご先祖様にお供えをしていました。
これが転じてお世話になった人へ贈り物をするようになり、
お盆には「お中元」を、年末には「お歳暮」をという形になりました。

お歳暮は、文字通り
年(歳)の暮れに日頃からお世話になっていたり親しくしている相手に送る心の贈り物です。
「いつもありがとう」
「これからも何卒よろしく」
というまごころを伝える意味でも大切にしていきたいですね。
普段お歳暮を贈らない方も、
今年は気分を変えて贈り物をしてみませんか。